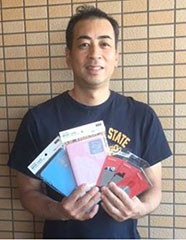(前回からの続き)第二の問題は、アセアン中心性そのものである。中国にとってみれば、この「中心性」を壊してアセアンの全会一致を崩せば良いだけだから、もっとも買収しやすい国を選んで、そこに重点的に資金をつぎ込めばよい。私が昨年カンボジアに言った際に聞いた話は、「アセアン中心性は、アセアンの大国側の論理に過ぎない。アセアン諸国と一緒に行動するときと、中国からの援助とを比べて、後者に利益があるのなら、別にアセアン中心性に義理立てする理由はない」という簡単明瞭な内容であった。つまり、中国のチェックブック外交にも問題はあるが、それを受け取る側にも課題が存在する。後発アセアンに十分に利益を供与できるだけの資源がアセアン側に存在しているわけではない。
第三の問題は、いわゆる「債務の罠」であって、これについても中国を批判するのは簡単だが、しかし九九年租借を締結したスリランカ政府がその契約書を十分に吟味しなかったのも事実である。むしろ、中国の側が国際的な評判を気にして、金銭供与国の事情を加味するなど、最近ではアプローチの仕方が変わってきている。
以上から分かることは、「自分の力」で対処できない国々が、「良い友人」を作って国際問題に対処するときの「国際協調」は、その維持が非常に難しいということである。この一〇月三一日からアセアン首脳会議が開催されるが、南シナ海問題が重要議題の一つになることは間違いない。いや、これまで何度議題になったか分からないが、そのたびに全会一致原則があるために、強い対処法について統一見解が出せずに来た。「アセアン中心性」が出ないと、それ以外の国々からのコミットメントを「ある程度」以上のものにはならない。その意味で、他国の抱える問題をどの程度「アセアン地域」全体の問題として捉えることができるかが大きな焦点となるだろう。
今の状態では、中国外交の「二歩前進、一歩後退」または「三歩前進、二歩後退」の論理に負けてしまう。アセアンの課題が、中国外交からの対処次第で決まるという「他力本願」的な状態では、いずれ徐々にジリ貧状態になる。かつて書いたように「江戸の敵を長崎で討つ」方式で、海洋法の範疇で海の問題を片付けようとしない中国は、あらゆる手段で「核心的利益」を実現しようとするだろう。
これに対し、アメリカはCSISが創設したアジア海洋透明性イニシアチブ(The Asia Maritime Transparency Initiative:AMTI)が常に南シナ海を監視している。また、「自由の航行」作戦を展開して、南シナ海における航行の自由を保障されるべく、活動を展開している。さて、日本はどうか。日本はベトナムやフィリピンに対して政府開発援助(ODA)の枠組みで海上保安庁の巡視船を供与することに成功した。しかし、常に漸増主義的で大きな変革があるわけではない。また、ここ一年香港で民主化運動が起こっているが、これに対しても比較的静観を決め込んでいる。南シナ海問題についても、ベトナムにとってみれば、アセアンを始め、多くの国との連携を「よき友人」として求めている。日本の外交は、一方でアメリカとの良好な関係も維持するが、他方で「イラク派遣」にはNOが言える。同時に、対中外交についても、国家主席の訪日を待ちながらも、批判すべきところは批判するものでないといけない。「外交」とは、自国の利益のみならず、地域全体の平和と安全を促進するものであるから、そこには「柔軟性」が存在しないといけないだろう。
伊藤 剛 氏
明治大学 教授
国際政治学研究 担当
米国デンバー大学大学院 卒
主な著書・論文
『同盟の認識と現実』(有信堂・2002年)
Alliance in Anxiety(New York : Routledge, 2003年)
『比較外交政策』(明石書店・2004年)
『自由の帝国』(翻訳・NTT出版・2000年)
|